シンガポールへの旅行や出張を考えたとき、「渡星」という言葉を目にして、「なぜシンガポールは星と書くんだろう?」と不思議に思ったことはありませんか?
そもそも、シンガポールという国名を漢字でどう書くのか、その正式な読み方や、1文字での略し方について、詳しく知りたいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は、シンガポールの漢字表記には「星港」といったおしゃれなバリエーションもあり、どの漢字をどのように使うのかには、とても興味深い歴史的な背景が関係しているのです。
 筆者
筆者この記事では、シンガポールという国名にまつわる漢字の様々な謎を、一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
- シンガポールの正式な漢字表記とその由来
- なぜ「星」という漢字が略称として使われるのか
- 「星港」や「狮城」など多様な漢字表記の背景
- 日本とシンガポールにおける漢字使用の違い
シンガポールを漢字で書くと?正式表記の由来


- 正式表記「新加坡」の読み方
- なぜ「坡」という漢字を使うのか
- 「星」という漢字が使われる理由
- なぜ「新」ではなく「星」を主に使うのか
- 「渡星」という言葉の由来について
正式表記「新加坡」の読み方
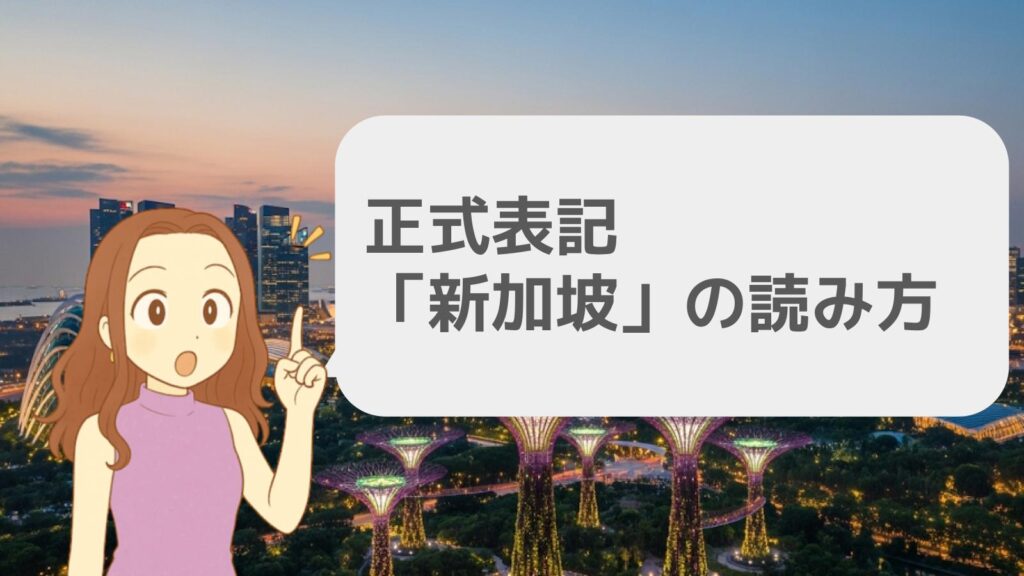
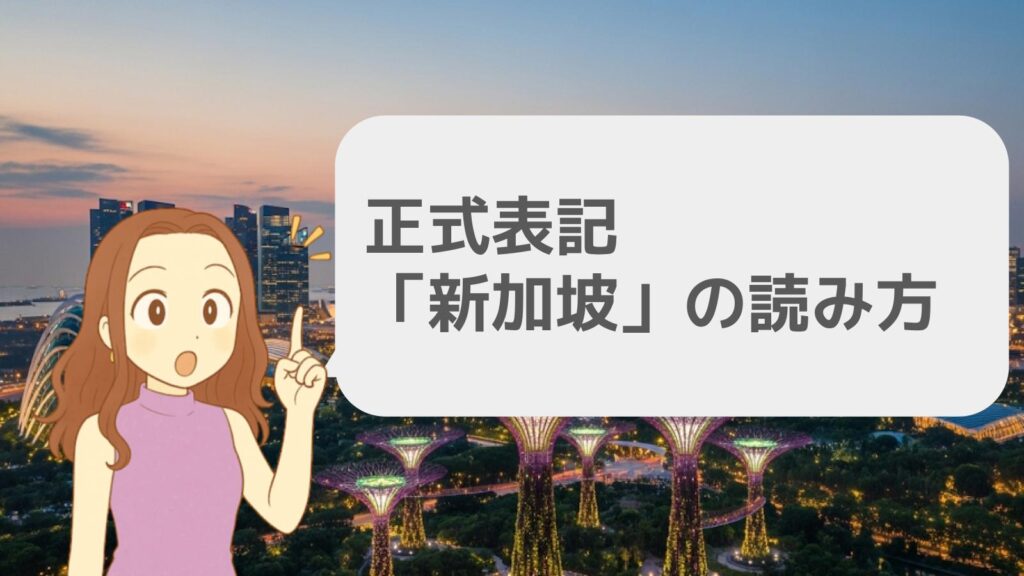
シンガポールの漢字における正式な表記は「新加坡」と定められています。
この読み方は、中国語(普通話)の発音である「Xīn jiā pō(シンジャポー)」に基づいています。日本語の「シンガポール」という音と、中国語の「シンジャポー」という響きが似ていることから、これらの漢字が当てられたと考えられますね。
ちなみに、この「新加坡」という表記が正式に決定されたのは、1972年4月25日のことでした。シンガポールが1965年に独立した後、国内の地名や通りの名前を統一する必要性が高まったのです。それまでは「新嘉坡」や「星加坡」といった、同じような音を持つ他の漢字表記も混在していましたが、政府の委員会によって「新加坡」に統一されることになりました。
なぜ「坡」という漢字を使うのか
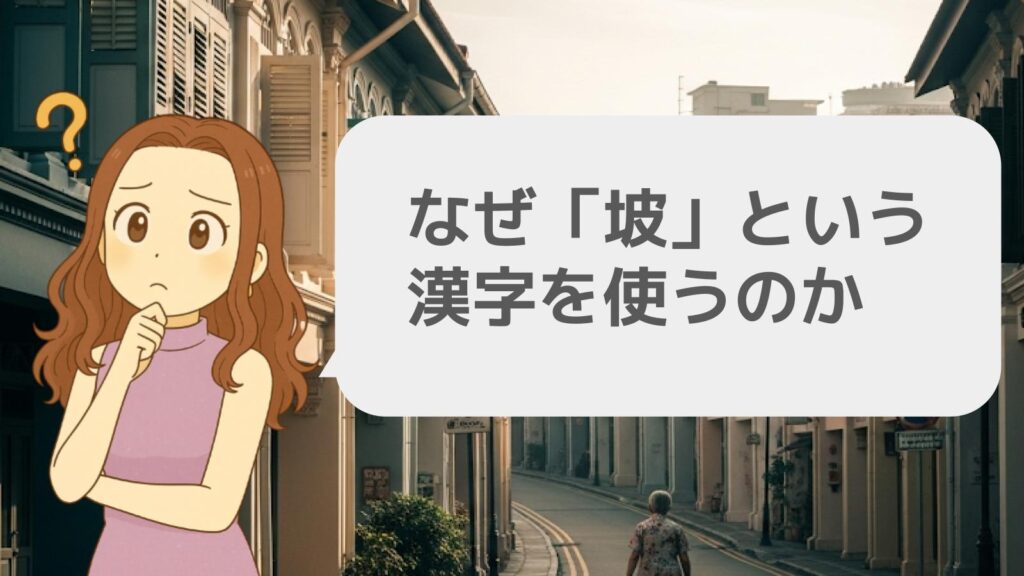
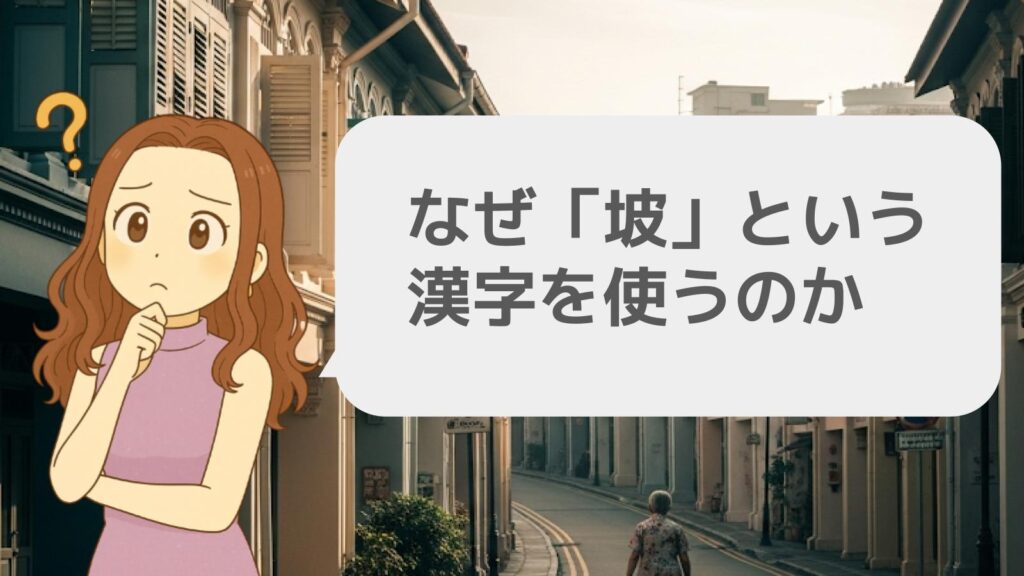
シンガポールの漢字表記「新加坡」に含まれる「坡」という文字には、実はシンガポールの地形的な特徴が関係しています。
この「坡」という漢字は、日本語で「坂」を意味します。かつてシンガポール川の両岸には、それぞれ「大坡(ダーポー)」と「小坡(シャオポー)」と呼ばれるエリアがありました。この地域は多くの中国系移民が暮らす中心地で、チャイナタウンなどが位置する大坡は、川岸にあるため坂になっていたのです。
多くの人々が生活する身近な場所の地形的特徴から、「坂」を意味する「坡」の字がシンガポールを象徴する漢字の一つとして定着していきました。
ちなみに、「新◯坡」という形の表記が歴史上初めて登場するのは、1840年にドイツ人宣教師カール・ギュツラフが記した「貿易通志」という書物です。ここには「新嘉坡」という文字で、当時のシンガポールが東南アジアの主要な貿易拠点であったことが記されています。
「星」という漢字が使われる理由
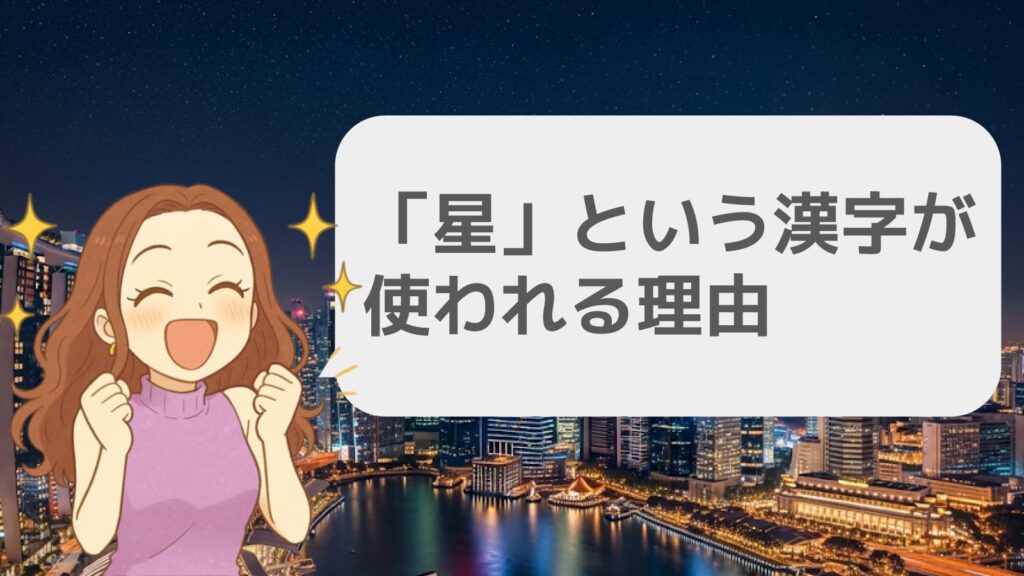
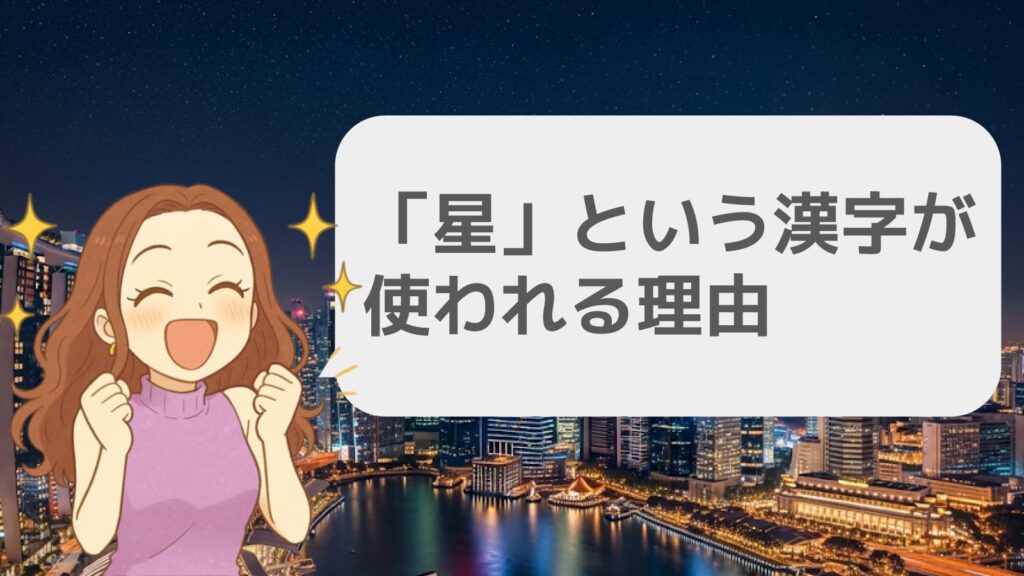
シンガポールの略称として、なぜ「星」という美しい漢字が使われるのでしょうか。
その理由は、正式表記が統一される前に使われていた複数の表記の一つ、「星加坡(シンガポー)」に由来します。こちらも中国語の発音は「Xīn jiā pō」であり、正式表記の「新加坡」とほとんど同じ響きです。
「新」と「星」は、中国語ではどちらも「シン(xīn)」に近い発音をします。そのため、意味合いや見た目の印象が良い「星」という漢字が、愛称のように広く使われるようになったと考えられます。国のシンボルとして使うなら、未来的で輝かしいイメージを持つ「星」の方が好まれたのかもしれませんね。
なぜ「新」ではなく「星」を主に使うのか
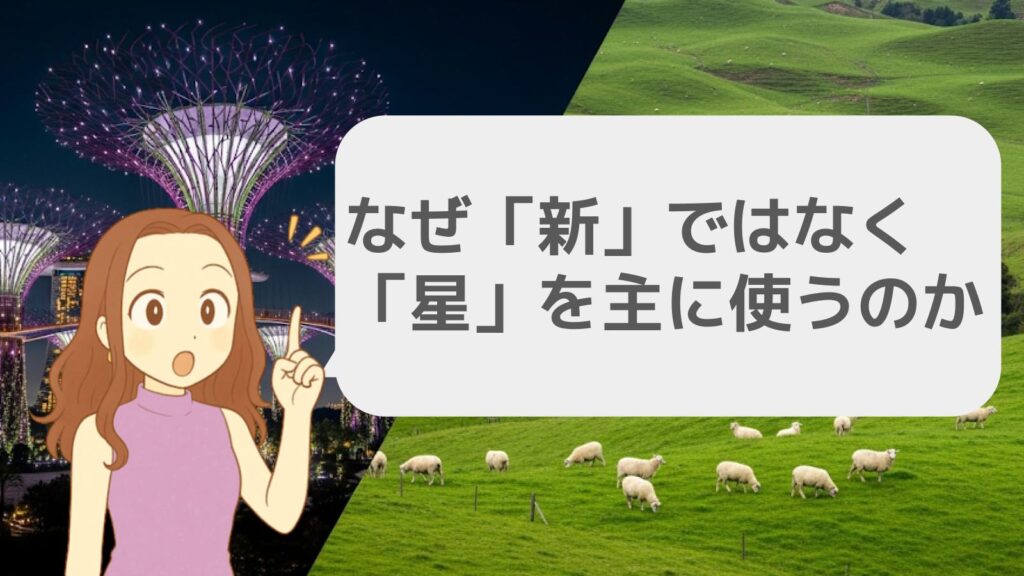
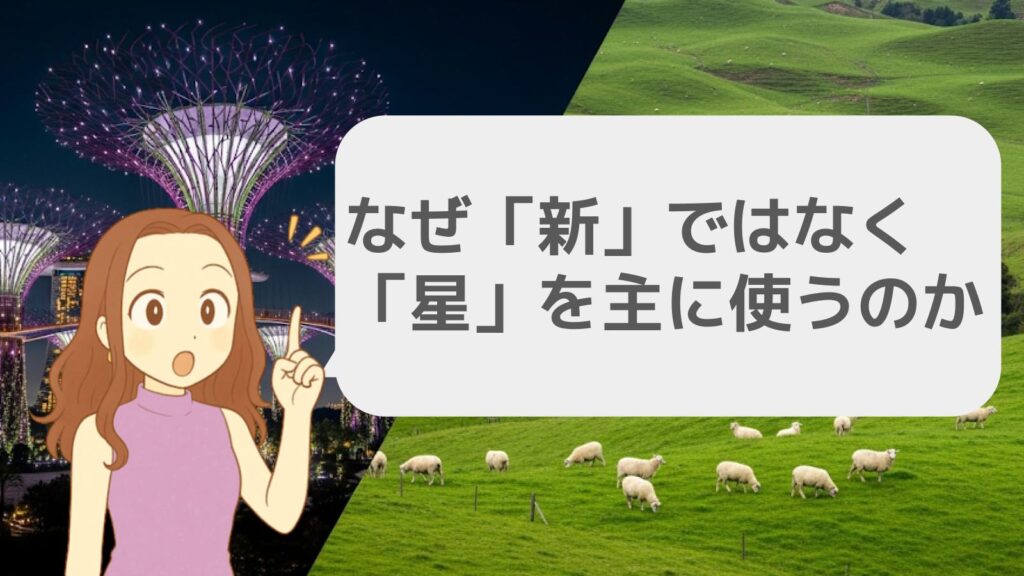
「新加坡」が正式な漢字表記であるにもかかわらず、略称として「新」ではなく「星」が好んで使われるのには、他の国との混同を避けるという、はっきりとした理由があります。
実は、「新」という漢字を国名の略称として使う国が、シンガポール以外にも存在するからです。それは、ニュージーランドです。ニュージーランドは漢字で「新西蘭」と表記されるため、もしシンガポールを「新」と略してしまうと、文脈によってはどちらの国を指しているのか分かりにくくなる可能性があります。
このような理由から、特に国際的な文脈や、他の国名と並べて表記する際には、混乱を避けるためにも「星」という漢字が非常に便利なのです。デザイン的な魅力だけでなく、実用的な側面からも「星」が選ばれてきたと言えます。
「渡星」という言葉の由来について
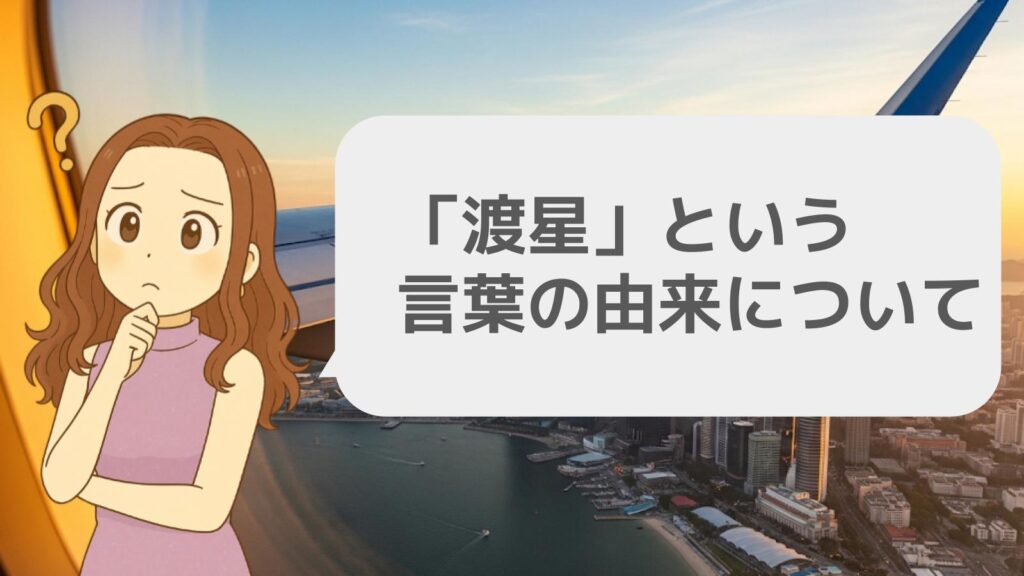
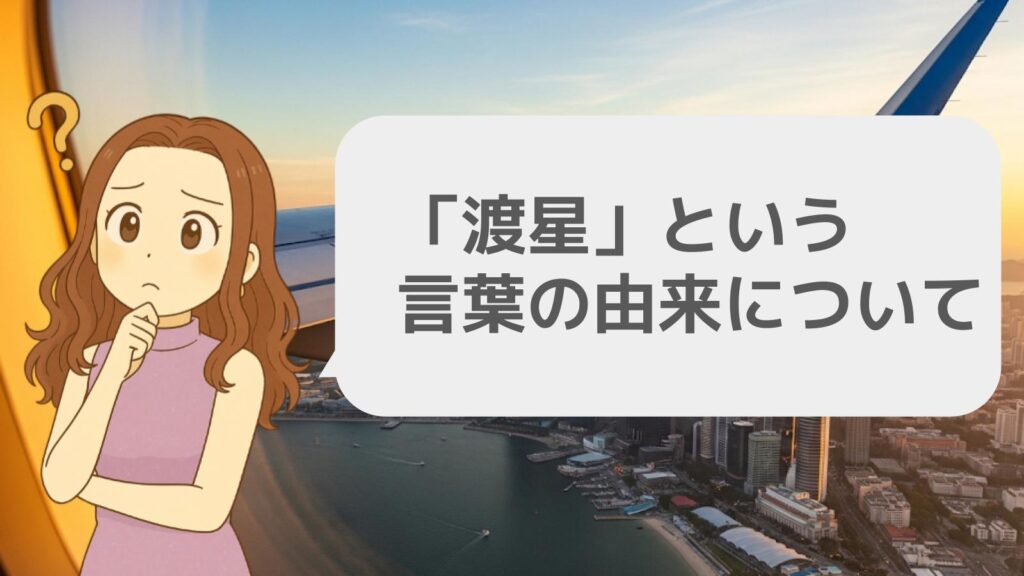
日本からシンガポールへ行くことを「渡星」と表現することがありますが、この言葉の由来も、これまで解説してきた漢字の歴史と深く関わっています。
前述の通り、「星加坡」という表記があったことから、シンガポールの略称として「星」が定着しました。日本語では、ある国へ渡航することを「渡+国名の漢字一文字」で表現する慣習があります。例えば、アメリカへ行くことを「渡米」、イギリスなら「渡英」と言うのと同じ考え方です。
この慣習に倣い、シンガポールの略称である「星」を使って「渡星」という言葉が生まれ、広く使われるようになりました。シンガポールの歴史と、日本語の言葉の作り方が組み合わさってできた、興味深い表現ですね。
シンガポールの漢字の様々なバリエーション
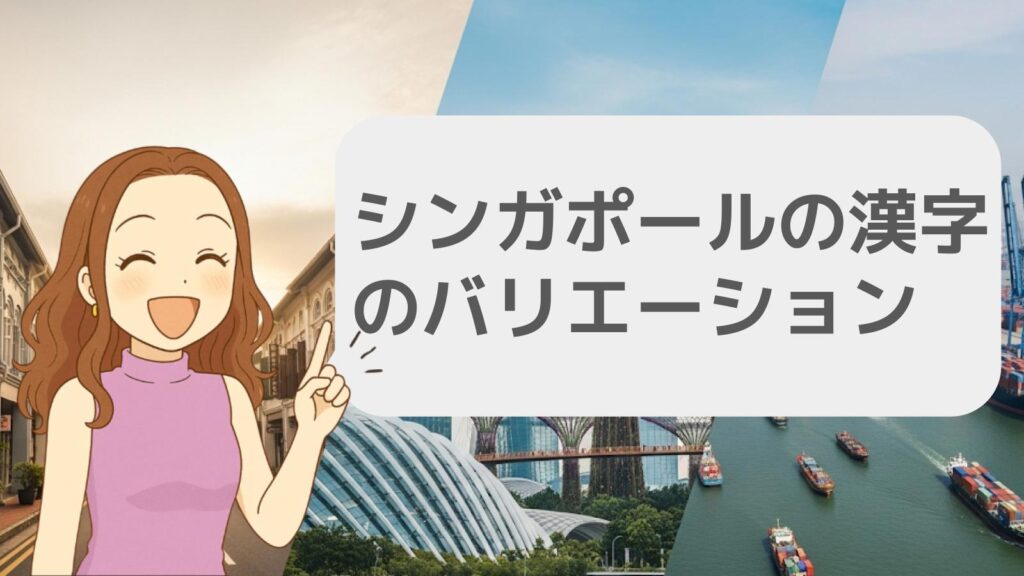
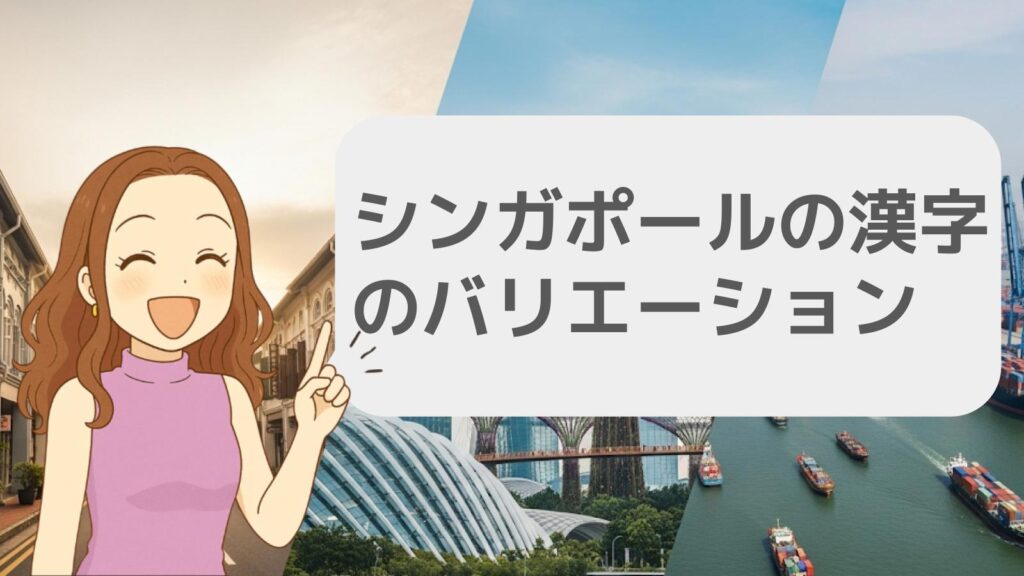
- シンガポールを漢字1文字で表す場合
- 「星洲」や「狮城」といった略称
- 他の国名の漢字表記との比較
- 「星港」という表記も使われる
- まとめ:シンガポールにおける漢字表記の変遷
シンガポールを漢字1文字で表す場合
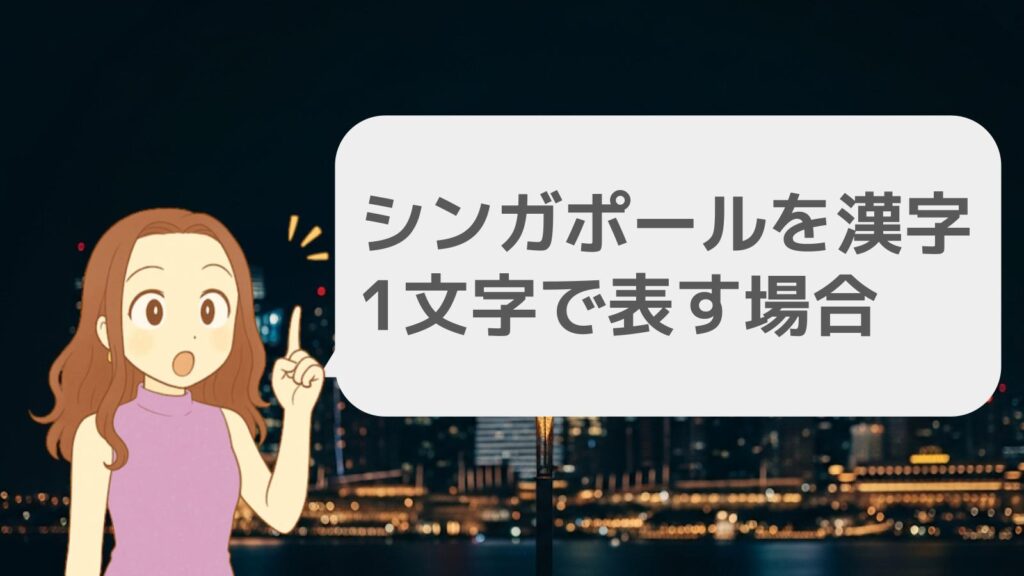
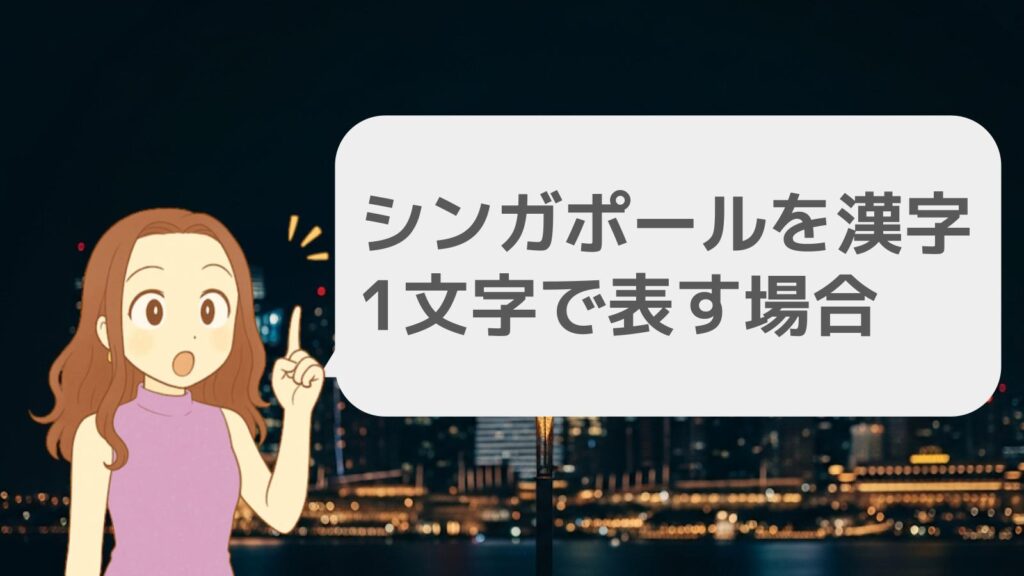
シンガポールを漢字1文字で表現する場合、最も一般的に使われるのは、やはり「星」です。この一文字で、多くの人がシンガポールを連想することができます。
ただし、一つ注意点があります。それは、日本の主要な新聞や通信社といった公式なメディアでは、シンガポールを「星」と略して表記することは、原則として認められていないという点です。
例えば、共同通信社の『記者ハンドブック』では、見出しなどで漢字一文字に略記して良い国名が定められており、そこには「仏(フランス)」や「豪(オーストラリア)」などは含まれていますが、「星」は入っていません。そのため、ニュース記事などで「星」の一文字を見かけることはほとんどないのです。
あくまで「渡星」のように、日常的な文脈や特定のコミュニティで使われる愛称のような位置づけだと考えると分かりやすいかもしれません。
「星洲」や「狮城」といった略称
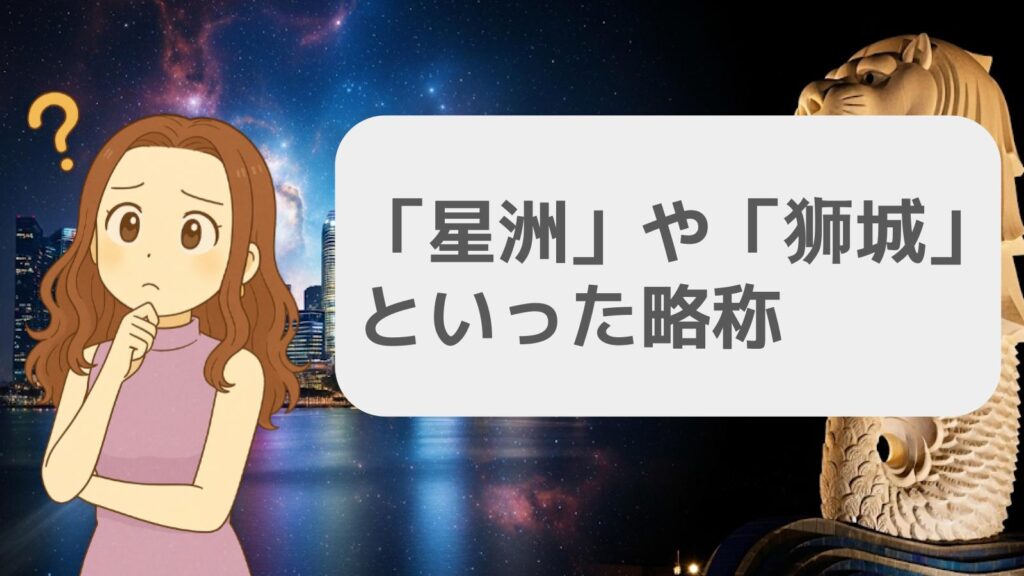
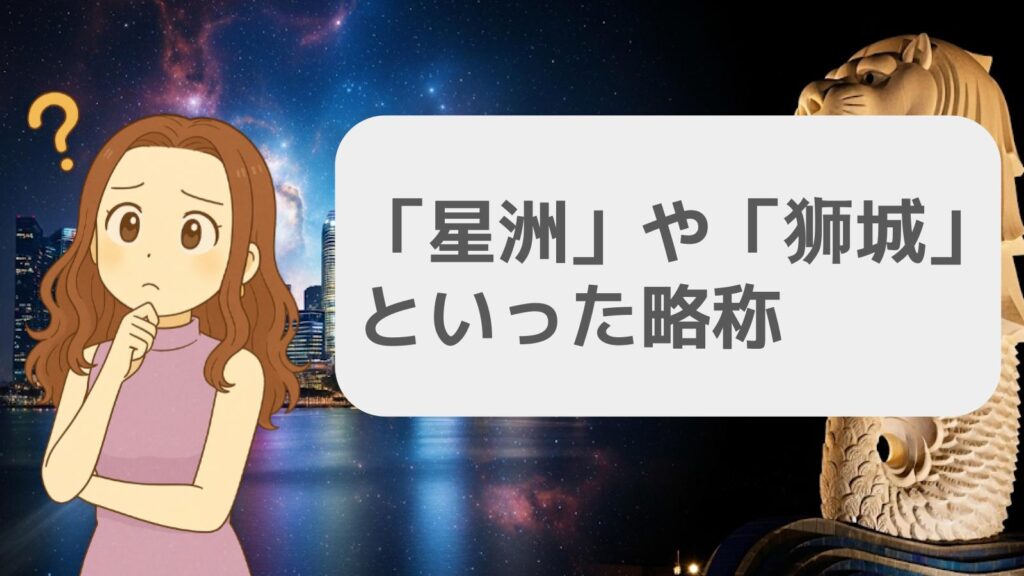
「星」以外にも、シンガポールには詩的でユニークな漢字の略称がいくつか存在します。その代表的なものが「星洲」と「狮城」です。
星洲(シン・チョウ)
「星洲」は、中国語で「Xīng zhōu(シン・チョウ)」と読みます。「星」はこれまで見てきた通りシンガポールを指し、「洲」は「島」や「大陸」を意味する漢字です。つまり、「星の島」といった美しい意味合いを持つ言葉になります。実際に、マレーシアに拠点を置く「星洲日報」という新聞社の名前にも、この表記が今なお使われています。
狮城(シー・チャン)
「狮城」は、中国語で「Shī chéng(シー・チャン)」と読み、意味は「ライオンの城」です。これは、シンガポールの国名の由来であるサンスクリット語「シンガプーラ(ライオンの街)」を、そのまま漢字に意訳したものです。マーライオン公園が有名なシンガポールにぴったりの、力強いイメージを持つ愛称ですね。
他の国名の漢字表記との比較


シンガポールの漢字表記の使われ方は、他の国と比較すると、その独特な背景がより一層際立ちます。特に、日本と中国での略称の扱いの違いは興味深い点です。
日本では、アメリカを「米国」、イギリスを「英国」と呼び、それぞれ「米」「英」と略します。これは、国名そのものを漢字で音訳した「亜米利加」や「英吉利」から来ています。一方で、シンガポールを「星国」と呼ぶことはあまり一般的ではありません。
以下の表は、いくつかの国における漢字表記と略称を比較したものです。
| 国名 | 正式な漢字表記(一例) | 中国語圏での一般的な略称 | 日本での一般的な略称 |
| シンガポール | 新加坡 | 星、新 | 星(非公式) |
| ニュージーランド | 新西蘭 | 新 | なし |
| アメリカ合衆国 | 亜米利加 | 美 | 米 |
| イギリス | 英吉利 | 英 | 英 |
| フランス | 仏蘭西 | 法 | 仏 |
| ドイツ | 独逸 | 徳 | 独 |
このように見ると、シンガポールの「星」という略称は、中国語圏での呼び方が日本にも影響を与えた、少し特殊なケースであることが分かります。日本の公式メディアが使わない一方で、日常的には広く浸透しているという点も、他の国にはあまり見られない特徴と言えるでしょう。
「星港」という表記も使われる
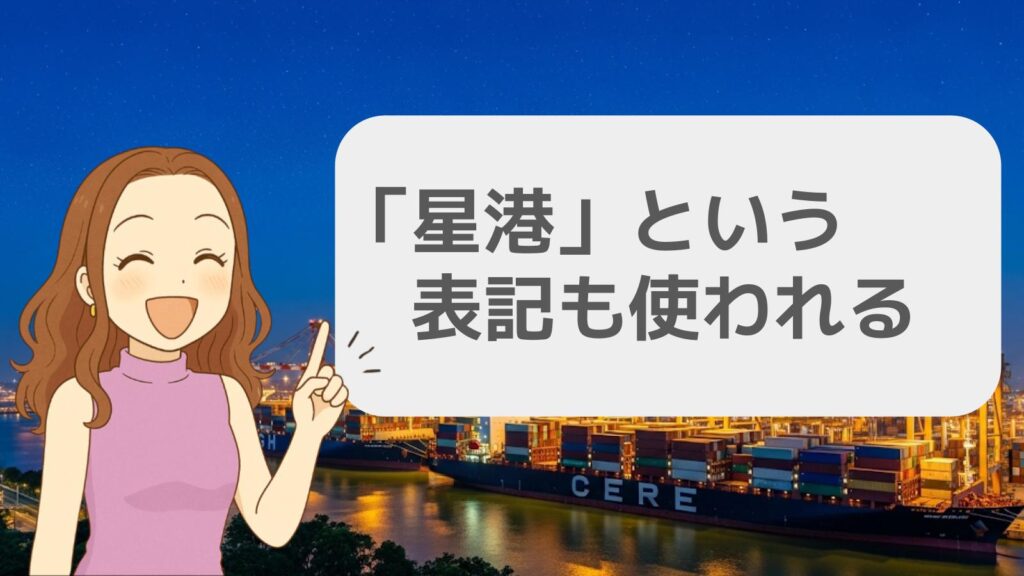
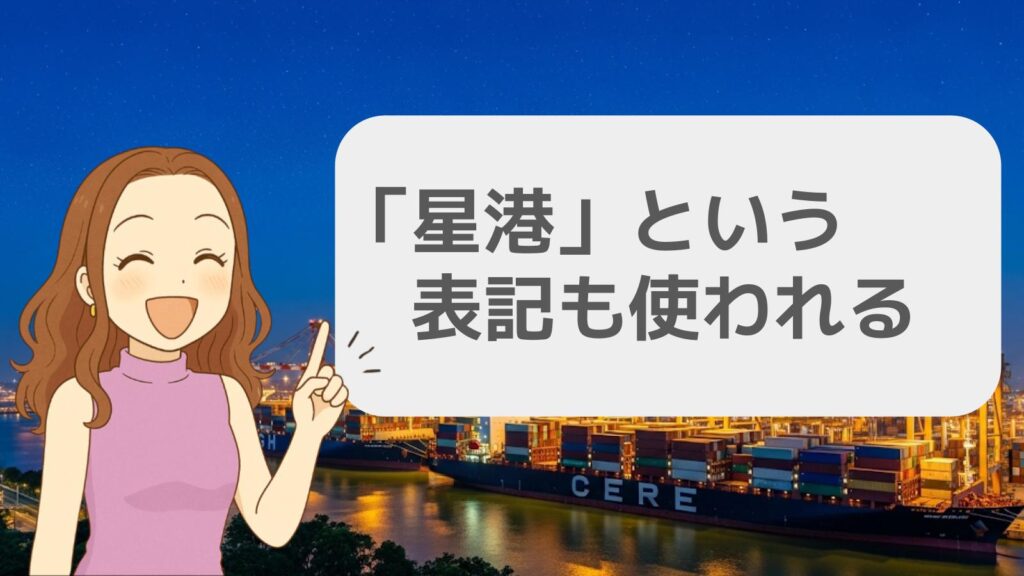
シンガポールの漢字表記の中には、「星港」という、港町としての歴史を感じさせる粋な表現も存在します。
この「星港」は、「星の港」と読むことができ、シンガポールの象徴である「星」と、その成り立ちに不可欠であった「港」という要素を組み合わせたものです。古くから国際的な貿易港として栄えてきたシンガポールの姿を、見事に表現した言葉ですね。
実際に、日本の仙台市には「純喫茶 星港夜(シンガポールナイト)」という名前のお店が存在します。これは、シンガポールのノスタルジックでおしゃれな夜をイメージして名付けられたのかもしれません。このように、正式な国名や略称としてだけでなく、文化的な文脈の中で、シンガポールの持つ独特の雰囲気を表す言葉として「星港」という漢字が使われることもあるのです。
まとめ:シンガポールにおける漢字表記の変遷


ここまで見てきたように、シンガポールの漢字表記は一つだけではなく、その歴史や文化の中で様々な表現が生まれてきました。最後に、この記事で解説した重要なポイントを振り返ってみましょう。
- シンガポールの公式な漢字表記は「新加坡」
- この表記は1972年に政府によって正式に統一された
- 読み方は中国語の「Xīn jiā pō(シンジャポー)」に由来する
- 「坡」の字はシンガポール川両岸の坂のある地形から来ている
- 最も一般的な1文字の略称は「星」
- 「星」は過去の表記「星加坡」に由来している
- 「新」ではなく「星」を使うのはニュージーランド(新西蘭)との混同を避けるため
- 「渡星」は日本の「渡+国名略称」という慣習から生まれた言葉
- 「星洲」は「星の島」を意味する美しい別称
- 「狮城」は「ライオンの城」を意味し国名の由来を反映している
- 「星港」は港町としてのシンガポールを象徴する粋な表現
- 日本の公式メディアでは「星」という略称は原則として使用されない
- 過去には「新嘉坡」など複数の漢字表記が混在していた
- 漢字表記の変遷はシンガポールの多文化な歴史を映し出している
- それぞれの漢字表記が持つ意味を知るとシンガポールへの理解が深まる



シンガポール観光の前に確認するべき、現地で役立つ情報をお伝えします!
- シンガポールでペットボトルの持ち歩きはOK?禁止事項を徹底解説
- シンガポールのトイレ事情を徹底解説!旅行前に知りたい全知識
- シンガポールのアラブストリート観光ガイド|グルメもお土産も満喫!
- シンガポールフードコート完全ガイド!おすすめからマナー、ホーカーまで解説
- シンガポールの漢字表記はなぜ星?読み方や由来を解説
- シンガポールとマレーシアの違いとは?歴史から旅行まで解説
- シンガポール旅行の持ち物リスト!必需品から服装まで解説
- シンガポール旅行で現金は必要?両替やカード事情を完全解説
- シンガポールカジノ完全ガイド!服装・予算・ルールを徹底解説
- シンガポールの罰金とサンダル規定!?旅行前に必読!
- シンガポールのチップは不要?ホテルやタクシーの相場を解説
- マーライオンはなぜ水を吐く?伝説から豆知識まで徹底解説!
- マリーナベイサンズ倒壊の噂は嘘?傾きの真相と安全性を解説
- マリーナベイサンズに安く泊まる方法|2025年版の料金と裏ワザ
- マリーナベイサンズ展望台の予約と無料で行く方法

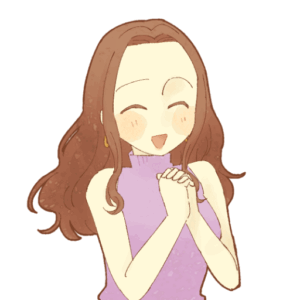
コメント