茨城県にある鹿島神宮。その奥参道にひっそりと佇む「要石(かなめいし)」について、あなたはどんなイメージをお持ちでしょうか?
 筆者
筆者もしかしたら、映画『すずめの戸締まり』で知った方や、地震と鯰(なまず)の伝説に興味を惹かれている方もいらっしゃるかもしれませんね。
東日本大震災の後にその存在意義が改めて注目されたこともありました。
この記事では、鹿島神宮の要石にまつわる様々な疑問にお答えしていきます。地震が起きる前の異変との関係や、要石をもし抜いたらどうなるのか、といった古くからの言い伝え。
また、石が割れたことはいつあったのかという疑問、不思議な出来事の記録、そして要石に呼ばれる人というスピリチュアルな側面にも触れていきます。
境内にある御手洗池が怖いと感じる理由や、参拝することでいただけるお守りのご利益まで、訪れる前に知っておきたい情報をぎゅっと詰め込みました。この記事を読めば、あなたの知らない要石の奥深い世界がきっと見えてきますよ。
- 鹿島神宮の要石にまつわる具体的な伝説や歴史
- 地震を鎮めるという信仰と不思議な逸話の数々
- 香取神宮の要石との違いや知られざる関係性
- 要石が持つスピリチュアルな意味と現代への影響
鹿島神宮のかなめいしとは?その伝説


- 要石を抜いたらどうなるという伝説
- 要石が割れたことはいつあったのか
- 東日本大震災と要石の関係
- 要石のお守りとそのご利益
- 映画すずめの戸締まりと要石
要石を抜いたらどうなるという伝説


鹿島神宮の要石について語られるとき、必ずと言っていいほど登場するのが「決して抜くことができない石」という伝説です。
この伝説を象徴する有名な逸話が、水戸黄門として知られる徳川光圀公にまつわるお話です。学問への探求心が非常に強かった光圀公は、「要石の根は一体どこまで続いているのか」という疑問を確かめるため、石の周りを掘らせることにしました。
なんと7日7晩もの間、大勢の人々が交代で掘り続けたそうです。しかし、掘っても掘っても石の根っこに辿り着くことはできませんでした。
そればかりか、掘り進めるうちに不思議と体調を崩す者や、怪我をする者が続出してしまったのです。このことから、さすがの光圀公も「これは人の手でどうこうできるものではない」と悟り、掘ることを諦めたと伝えられています。
この逸話は、要石が地表に見えている部分はほんの氷山の一角に過ぎず、その本体は地球の奥深くまで達しているという信仰を強く裏付けるものとなりました。
ですから、「もし抜いたらどうなるのか」という問いの答えは、「そもそも人の力では絶対に抜くことはできない」というのが古くからの考え方なのです。
要石が割れたことはいつあったのか


これほどまでに強固な伝説を持つ要石ですから、「過去に壊れたり割れたりしたことはあるの?」と気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。
記録を調べてみても、鹿島神宮の要石そのものが自然災害や人の手によって「割れた」という記述は見当たりません。この事実は、要石が持つ神秘性や神聖さを一層高めているように感じられます。
ただ、ここで注目したいのが、2011年に発生した東日本大震災の時のことです。この未曾有の大地震によって、鹿島神宮の入口にあった御影石の大きな大鳥居は、残念ながら根元から倒壊してしまいました。神社で最も象徴的な建造物の一つが崩れてしまうほどの、凄まじい揺れだったことが分かります。
しかし、そのような状況下でも、要石は以前と何ら変わらぬ姿でそこにあり続けました。このことから、要石の伝説は単なるお話ではなく、物理的な強さをも伴ったものであると、多くの人々が再認識することになったのです。
つまり、石が割れたことがあるかという問いに対しては、「そのような記録はなく、むしろ大災害をも乗り越えてきた」と考えるのが自然でしょう。
東日本大震災と要石の関係


前述の通り、東日本大震災は鹿島神宮にも大きな爪痕を残しましたが、同時に要石の存在意義を改めて浮き彫りにする出来事でもありました。
地震大国である日本では、古くから地震は人々の生活と切り離せないものでした。特に鹿島神宮のある関東地方は、地震を鎮める「鹿島大明神」への信仰が篤い地域です。その信仰の中心にあるのが、地震を起こす大鯰の頭を押さえつけているとされる、この要石なのです。
東日本大震災という大きな揺れを経験したことで、人々は改めて自然の力の大きさと、それに対する畏怖の念を抱きました。そして、神宮の象徴である大鳥居が倒壊する中でも、静かに鎮座し続ける要石の姿に、一種の希望や心の支えを見出した方も少なくありませんでした。
この出来事を通じて、要石は単なる伝説の石ではなく、人々の不安を受け止め、平穏な日常への祈りを捧げる対象として、より一層深い意味を持つようになったと言えます。災害を乗り越え、変わらずにあり続けるその姿は、私たちに目には見えない力の存在を静かに語りかけているのかもしれませんね。
要石のお守りとそのご利益
鹿島神宮を訪れた際に、ぜひ注目していただきたいのが要石にちなんだお守りです。神社の授与所では、様々な種類のお守りや御札をいただくことができますが、中でも要石のご利益が込められたものは特別な意味を持っています。
要石に期待されるご利益
要石の最も代表的なご利益は、やはり「地震除け」や「災難除け」です。大地を鎮める力を持つ石であることから、私たちの身に降りかかる様々な災いから守ってくれると信じられています。
また、その信仰はさらに広がって、物事の「要」をしっかりと押さえるという意味にも繋がっています。
- 基盤を固める: 仕事や家庭など、人生の土台を安定させたい時に。
- 不動の心: 周囲の状況に揺さぶられない、強い精神力を持ちたい時に。
- 大切なものを守る: 守りたい人や場所、関係性をしっかりと繋ぎ止めたい時に。
このように、大地に深く根を張る要石の姿は、私たちの生活における様々な「安定」や「守護」の願いを叶える力があるとされているのです。
もちろん、お守りを持つだけで全てが解決するわけではありません。しかし、このお守りを身につけることで、鹿島の大神様や要石の力がいつもそばで見守ってくれているという安心感を得ることができ、それが日々の生活を前向きに進めるための支えになるのではないでしょうか。
映画すずめの戸締まりと要石
近年、鹿島神宮の要石が再び脚光を浴びるきっかけとなったのが、2022年に公開された新海誠監督のアニメーション映画『すずめの戸締まり』です。
この物語の中では、日本各地で災いを引き起こす「ミミズ」を封じ込めるために、「要石」が非常に重要な役割を果たします。映画を観た方はご存じかもしれませんが、物語の鍵を握るキャラクターである白猫のダイジンは、実は要石が姿を変えた存在として描かれているのです。
映画では、この要石が抜けてしまったことから災いが始まります。これは、鹿島神宮に伝わる「要石が地震(大鯰)を押さえている」という古来の伝説と、その根底にある思想が同じであることが分かりますね。
この映画のヒットにより、これまで神社や歴史にあまり興味がなかった若い世代の人々も、要石の存在を知ることになりました。物語を通じて、日本人が古くから自然災害と共に生き、それを鎮めるための祈りや物語を大切にしてきた文化に触れるきっかけになったのです。
このように、鹿島神宮の要石の伝説は、形を変えながらも現代のクリエイターにインスピレーションを与え、新しい物語として私たちの心に届けられています。古くからの信仰が、現代のカルチャーと繋がる興味深い事例と言えるでしょう。



私は映画館で見たのですが、涙を堪えきれませんでした
鹿島神宮かなめいしにまつわる不思議な話
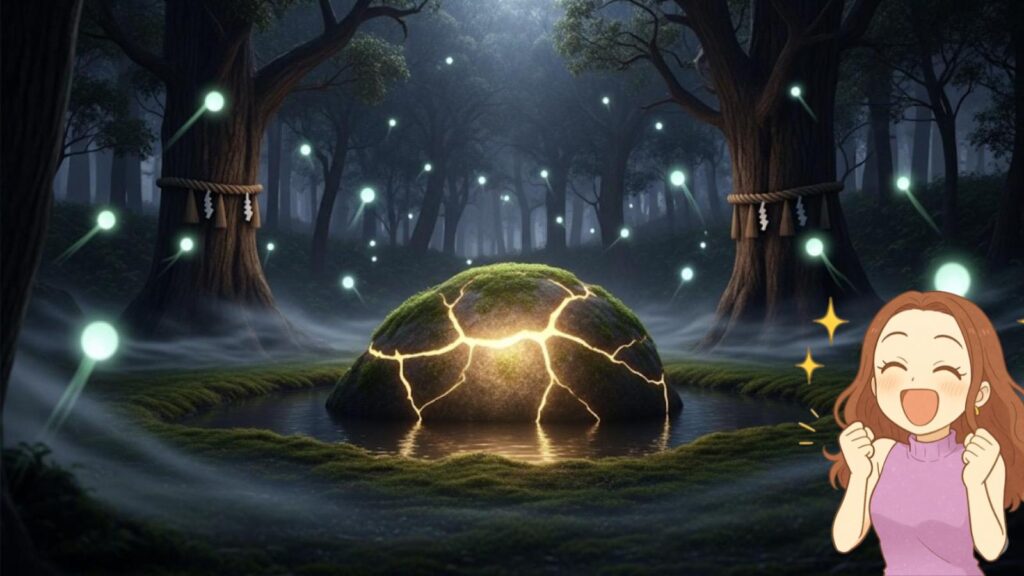
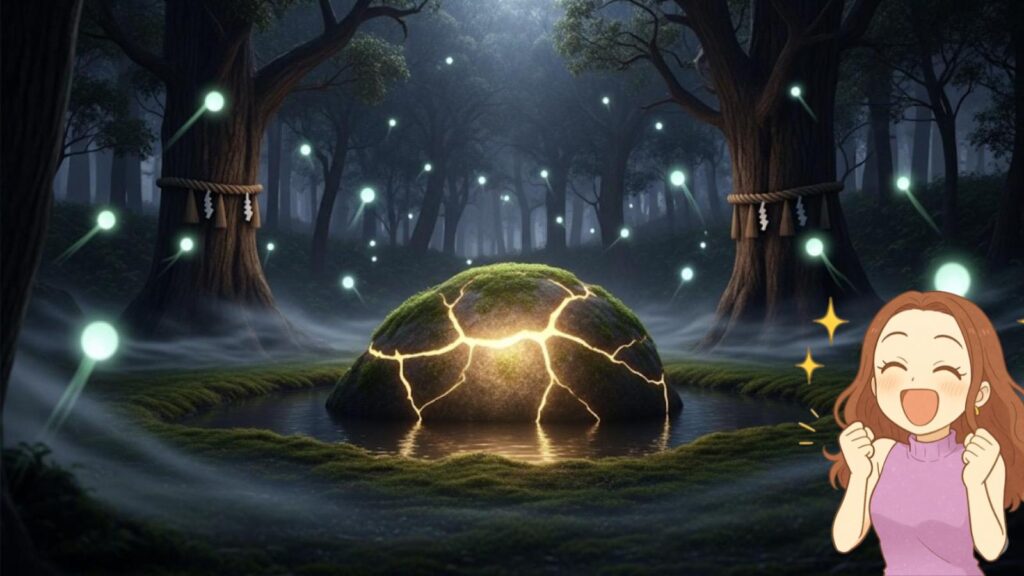
- 地震の前の異変と要石の言い伝え
- 要石にまつわる不思議な出来事
- 要石に呼ばれる人の特徴とは
- 御手洗池が怖いと言われる理由
- 鹿島神宮の要石が持つ重要な意味
地震の前の異変と要石の言い伝え
昔から、大きな地震が起きる前には何らかの「異変」が起こると言い伝えられてきました。例えば、井戸の水が枯れたり、動物たちが普段と違う行動をとったり、といった話を聞いたことがあるかもしれません。
このような自然界のサインと、地震を鎮める要石の信仰は、古くから深く結びついて考えられてきました。
もともと、地震を起こす存在は必ずしも鯰(なまず)だけではありませんでした。鎌倉時代の書物には、地面の下に巨大な「地震蟲(じしんむし)」という怪物がいるという記述が見られます。
そして、その怪物の頭を鹿島大明神が要石で押さえつけている図が描かれているのです。時代が下り、江戸時代になると、この地震蟲のイメージが、地震を予知する能力を持つとされる鯰に置き換わっていったと考えられています。
つまり、人々は地震の前の異変を敏感に感じ取り、それが地中の巨大な存在(蟲や鯰)が暴れようとしている兆候だと捉えました。そして、その活動を唯一抑え込めるのが鹿島神宮の要石であると信じ、平穏を祈ってきたのです。この信仰は、科学的な解明ができなかった時代に、人々が自然の脅威と向き合うための知恵であり、心の拠り所だったのかもしれませんね。
要石にまつわる不思議な出来事
鹿島神宮の要石には、科学では説明できないような不思議な出来事がいくつも語り継がれています。
前述の通り、徳川光圀公が7日7晩掘っても根元に辿り着けなかったという逸話は、その代表格です。これは単に「石が大きい」という話だけでなく、神聖なものに人の力が及ばないという、神秘的な領域を示唆しているようです。
また、鹿島神宮の要石には、興味深いパートナーの存在があります。それは、千葉県香取市にある香取神宮の要石です。二つの神宮は利根川を挟んで鎮座しており、古くから非常に密接な関係にありました。
| 鹿島神宮の要石 | 香取神宮の要石 | |
| 役割 | 大鯰の「頭」を押さえている | 大鯰の「尻尾」を押さえている |
| 形状 | 地表部分が少し凹んでいる(凹型) | 地表部分が丸く盛り上がっている(凸型) |
このように、二つの要石は対の関係になっており、地中の奥深くで繋がっているという伝説まであります。鹿島の石が凹型で、香取の石が凸型というのも、まるで二つで一つのパーツのようで、想像が膨らみますね。
さらに、鹿島神宮の要石のルーツを辿ると、宮崎県の高千穂神社にある「鎮石(しずめいし)」に行き着くという説もあります。高千穂神社の案内板には、鹿島神宮創建の際にこの鎮石が贈られ、要石となったと記されているそうです。この話が事実であれば、要石の力は遠く神話の里から受け継がれたもの、ということになります。
これらの逸話は、要石が単なる一つの石ではなく、広大なネットワークの中で日本の大地を守っているという壮大な物語を感じさせてくれます。
要石に呼ばれる人の特徴とは


パワースポットなどを訪れる際に、「神様に呼ばれる」という表現をすることがあります。鹿島神宮の要石もまた、特定のタイミングで人を引き寄せることがある、と言われることがあります。
もちろん、これは科学的な話ではなく、あくまでスピリチュアルな観点からのお話です。一般的に、要石のような場所に「呼ばれる」とされる人には、いくつかの特徴や共通点が見られることがあるようです。
- 人生の転換期を迎えている人: 新しい仕事を始める、引っ越しをする、結婚するなど、生活の基盤が大きく変わるタイミングにいる方は、無意識に「安定」を求めて要石に惹かれることがあるかもしれません。
- 物事を始めようとしている人: これから何か大きなプロジェクトや目標に向かって進もうとしている時、その土台をしっかりと固めたいという願いが、要石への関心に繋がることがあります。
- 心が揺らいでいる人: 不安や迷いがあり、精神的な支柱を求めている時にも、不動の象徴である要石のエネルギーに触れたくなると言われます。
言ってしまえば、これは特別な人にだけ起こることではありません。あなたがもし今、この記事を読んで「鹿島神宮の要石が気になる」と感じているのであれば、それもまた何かのご縁であり、「呼ばれている」サインなのかもしれませんね。
大切なのは、自分の心の声に耳を傾け、惹かれる気持ちを素直に受け止めること。そうすることで、参拝がより一層意味深いものになるのではないでしょうか。
御手洗池が怖いと言われる理由
鹿島神宮の境内には、要石と並んで多くの人が訪れる神秘的な場所「御手洗(みたらし)池」があります。この池は、澄み切った湧水で知られる美しい場所ですが、一方で一部の人からは「少し怖い」と感じられることもあるようです。
この「怖い」という感情は、決して心霊的な意味合いではありません。むしろ、その場所が持つ神聖さや、自然の圧倒的な存在感から来る「畏怖(いふ)」の念に近いものと考えられます。
なぜ畏怖の念を抱くのか
- 驚くほどの透明度: 御手洗池は、大人が入っても胸まで浸かるほどの深さがあるにもかかわらず、池の底の砂までくっきりと見えるほど水が澄んでいます。この、ありのままを見通すような透明感が、人の心を少しざわつかせるのかもしれません。
- 静寂と森の深さ: 池は鬱蒼とした木々に囲まれており、周辺は非常に静かです。この静けさが、日常の喧騒から切り離された別世界のような雰囲気を作り出し、神聖な緊張感を生んでいます。
- 禊(みそぎ)の場としての歴史: 古来、鹿島神宮に参拝する人々は、この池で身を清める「禊」を行ってから神前へと進みました。現在でも大寒禊が行われるなど、ここは神聖な儀式の場です。そうした歴史が、場所に特別な空気感を与えているのです。
このように、御手洗池が「怖い」と感じられるのは、その美しさと神聖さが極まっているからこその感情と言えます。もし訪れる機会があれば、ぜひその清らかな水の流れと、深い静寂に包まれた空間を五感で感じてみてください。心が洗われるような、特別な体験ができるはずです。
鹿島神宮の要石が持つ重要な意味
- 鹿島神宮の要石は地震を鎮めるという伝説の中心にある
- 地表に見えるのはごく一部で地下に巨大な本体が続くとされる
- 徳川光圀が7日7晩掘っても底に届かなかった逸話が有名
- もし抜いたらどうなるかという問いの答えは「そもそも抜けない」
- 過去に石が割れたという記録は見つかっていない
- 東日本大震災で大鳥居が倒壊する中でも要石は無事だった
- ご利益は地震除けや災難除け、人生の基盤安定など
- 要石にちなんだお守りが授与所で頒布されている
- 地震を起こす存在は元々「地震蟲」で後に「大鯰」となった
- 千葉県の香取神宮の要石と対の関係にある
- 鹿島の要石は凹型で鯰の頭、香取は凸型で尻尾を押さえる
- ルーツは宮崎県の高千穂神社の「鎮石」という説もある
- 映画『すずめの戸締まり』で災いを封じる重要な役割として登場した
- 人生の転機や安定を求める人が惹かれる「呼ばれる」ことがある
- 要石は日本の大地と人々の心の平穏を守る象徴的な存在である



茨城旅行に行く前に知りたい情報を記事にまとめてあります!ぜひ見ていってください。
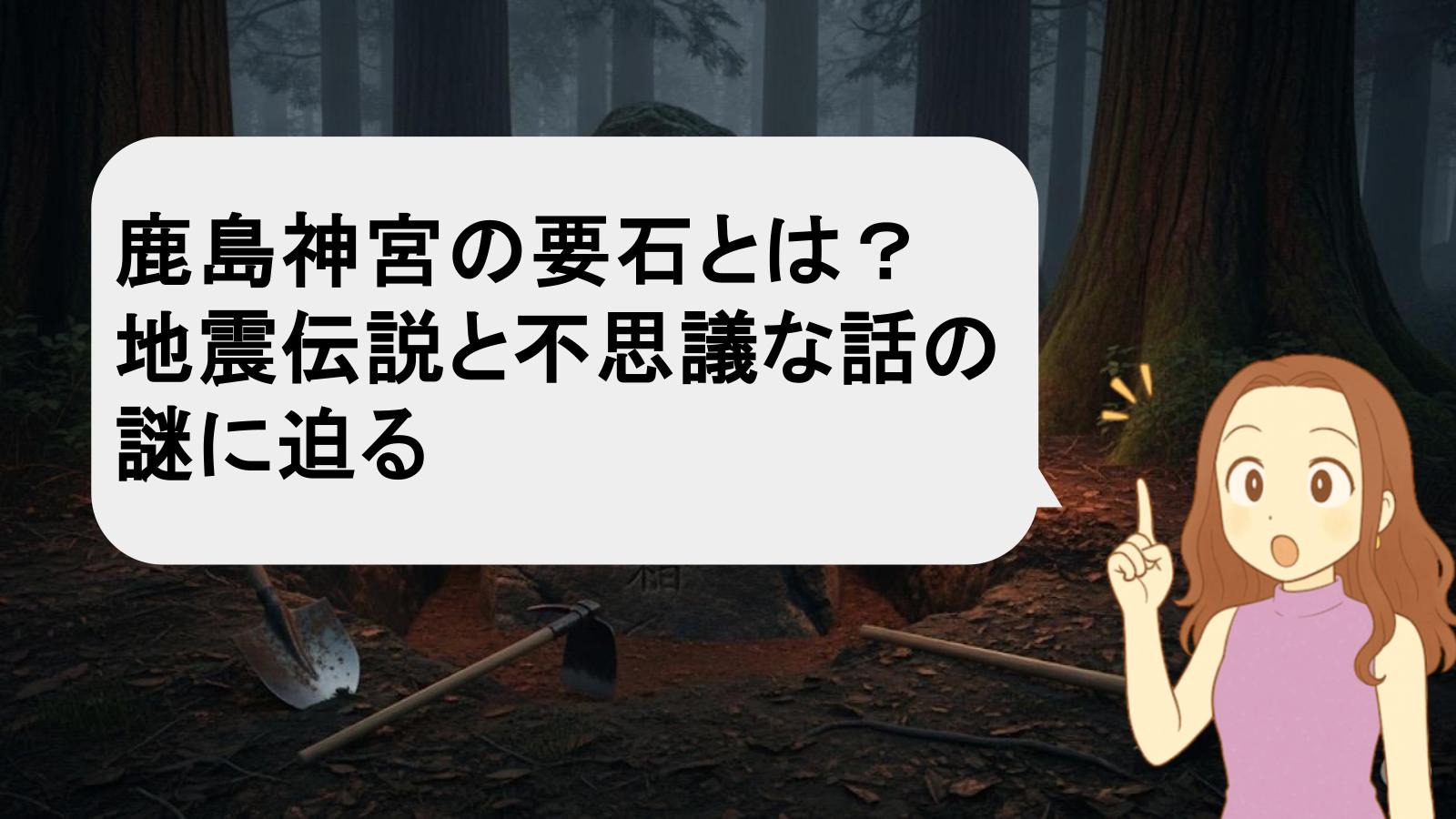
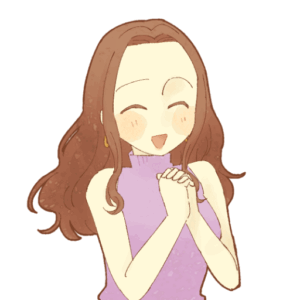
コメント