「大英博物館の盗品」について調べているあなたは、もしかしたら、その言葉の裏にある複雑な背景に疑問を感じているのかもしれませんね。世界最大級の博物館がなぜこのような呼ばれ方をするのか、気になりますよね。
 筆者
筆者この記事では、大英博物館の収蔵品にまつわる長年の議論について、一つひとつ丁寧に解説していきます。
帝国主義が花開いた時代の略奪の歴史から、植民地支配と文化財収集の関わり、そして特に有名とされるロゼッタ・ストーンのような収蔵品の入手経緯まで、その背景を深く掘り下げます。
また、今も続く各国からの返還要求の問題や、大英博物館はなぜ返さないのかという主張、そして「盗品一覧」は存在するのか、収蔵品全体におけるそうした品々の割合はどのくらいなのか、といった具体的な疑問にもお答えします。
中には、ツタンカーメンのマスクが大英博物館にあり返還問題になっているのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、その点に関する事実もしっかりと明らかにしていきますよ。
この記事を最後まで読めば、あなたが抱える疑問がきっと解消されるはずです。
- 「大英博物館の盗品」と呼ばれる歴史的背景
- 特に有名な収蔵品とその入手をめぐる経緯
- なぜ文化財が返還されないのかという理由と各国の主張
- 近年の盗難事件を含めた大英博物館の現状
大英博物館の盗品とされる収蔵品の概要


- 帝国主義と略奪の歴史
- 植民地支配が背景にある文化財
- 特に有名とされる収蔵品
- ロゼッタ・ストーンの入手経緯
- ツタンカーメンマスク大英博物館の返還は?
- 盗品一覧は存在するのか
- 略奪品とされるものの割合
帝国主義と略奪の歴史


大英博物館のコレクションが「略奪品」と呼ばれる背景には、18世紀から19世紀にかけての帝国主義の時代が深く関わっています。この時代、イギリスをはじめとするヨーロッパの列強は、世界各地へ進出し、その影響力を拡大させていました。
当時、古代文明の遺物を本国に持ち帰ることは、国の威信や学術的な先進性を示すステータスシンボルだと考えられていたのです。そのため、外交官や軍人、探検家たちが競うようにして、エジプトやギリシャ、メソポタミアといった地域の貴重な文化財を収集しました。
もちろん、当時は文化財保護に関する国際的なルールも未整備で、現代の価値観で見れば問題のある手段で収集されたものも少なくありません。
言ってしまえば、力を持つ国が、その力を背景に文化財を手に入れることが半ば公然と行われていた時代だったのです。このような歴史的経緯から、大英博物館のコレクションの一部は「略奪の歴史の象徴」と見なされ、批判の対象となることがあります。
植民地支配が背景にある文化財


コレクションの一部には、イギリスの植民地支配が直接的な背景となって収集されたものも含まれています。植民地という圧倒的な力関係の中で、文化財の「寄贈」や「購入」が行われたケースがこれにあたります。
形式上は合法的な手続きを踏んでいたとしても、その裏には植民地側の弱い立場があったことは想像に難くありません。例えば、現地の支配者や有力者が、宗主国であるイギリスの歓心を買うため、あるいは関係を良好に保つために、貴重な文化財を献上したという事例も指摘されています。
また、軍事行動の際に「戦利品」として持ち去られた文化財も存在します。1897年のベニン遠征でイギリス軍が持ち去った「ベニン・ブロンズ」などがその代表例です。
これらの文化財は、もともとあった場所から引き剥がされ、遠く離れたイギリスの地で展示されることになりました。このように考えると、植民地支配という歴史の側面を抜きにして、この問題を語ることはできないのです。
特に有名とされる収蔵品


大英博物館には約800万点もの収蔵品があると言われていますが、その中でも特に返還要求の声が強く、議論の的となっている文化財がいくつかあります。これらは博物館の目玉展示品でもあるため、問題がより複雑になっています。
どのようなものが議論の対象となっているのか、代表的なものを下の表にまとめてみました。
| 文化財 | 由来国 | 概要と論点 |
| エルギン・マーブル | ギリシャ | 19世紀初頭にイギリスの外交官エルギン伯爵がパルテノン神殿から削り取って持ち帰った大理石彫刻群。ギリシャ政府は一貫して返還を要求しています。 |
| ロゼッタ・ストーン | エジプト | 1799年にナポレオン軍が発見したものを、その後イギリス軍がフランス軍から戦利品として獲得。エジプトは自国の歴史を解明する鍵として返還を求めています。 |
| ベニン・ブロンズ | ナイジェリア | 1897年にイギリス軍がベニン王国から略奪したとされる数千点の青銅および象牙製品群。近年、返還の動きが一部で進んでいます。 |
| モアイ像(ホア・ハカナナイア) | チリ(イースター島) | 1868年にイギリスの軍艦が島から持ち出したもの。島の先住民ラパヌイの人々が精神的なつながりのある像の返還を強く望んでいます。 |
これらの文化財は、それぞれが持つ歴史的・文化的価値が非常に高い一方で、その入手経緯をめぐって今なお激しい議論が交わされているのです。
ロゼッタ・ストーンの入手経緯
大英博物館の展示品の中でも、おそらく最も知名度が高いのが「ロゼッタ・ストーン」ではないでしょうか。古代エジプトの象形文字(ヒエログリフ)解読の鍵となった、歴史的に非常に価値のある石碑です。
このロゼッタ・ストーンの入手経緯は、少し複雑です。最初に発見したのは、1799年にエジプトへ遠征していたナポレオン率いるフランス軍でした。しかし、その後、イギリス軍がエジプトでフランス軍を破ります。そして、1801年の降伏協定に基づき、フランス軍が収集した古代の遺物を含むロゼッタ・ストーンは、イギリスの手に渡ることになったのです。
つまり、イギリスがエジプトから直接略奪したというよりは、「フランス軍との戦争の戦利品」として獲得した、という経緯があります。ただ、エジプト側から見れば、自国の地で発見された最も重要な文化財が、ヨーロッパ列強間の争いの結果としてイギリスに渡ってしまった、という構図になります。そのため、エジプト政府は長年にわたり、文化的主権の象徴としてロゼッタ・ストーンの返還を求め続けているわけです。
ツタンカーメンマスク大英博物館の返還は?


「ツタンカーメンの黄金のマスクも大英博物館にあって、返還問題になっているのでは?」と思われている方が、実は少なくないようです。きらびやかで有名な遺物なので、大英博物館のイメージと結びつきやすいのかもしれませんね。
しかし、これは明確に誤解です。ツタンカーメンの墓は1922年にイギリスの考古学者ハワード・カーターによって発見されましたが、その際の発掘品は、当時のエジプトの法律に基づき、原則としてすべてエジプト国内に残されました。
黄金のマスクの現在の所蔵場所
したがって、ツタンカーメンの黄金のマスクは、一度も大英博物館に収蔵されたことはなく、発見以来ずっとエジプトにあります。現在は、カイロにあるエジプト考古学博物館の至宝として、厳重に保管・展示されています。将来的には、ギーザで建設中の大エジプト博物館に移される予定です。
なぜ誤解が生まれたのか
このような誤解が生まれる背景には、やはり大英博物館が古代エジプトのコレクションを多数所蔵しているという事実があるからでしょう。ロゼッタ・ストーンやラムセス2世の巨像など、あまりにも有名なエジプトの遺物がロンドンにあるため、「ツタンカーメンのマスクも同じなのでは?」という連想が働きやすいのだと考えられます。
盗品一覧は存在するのか
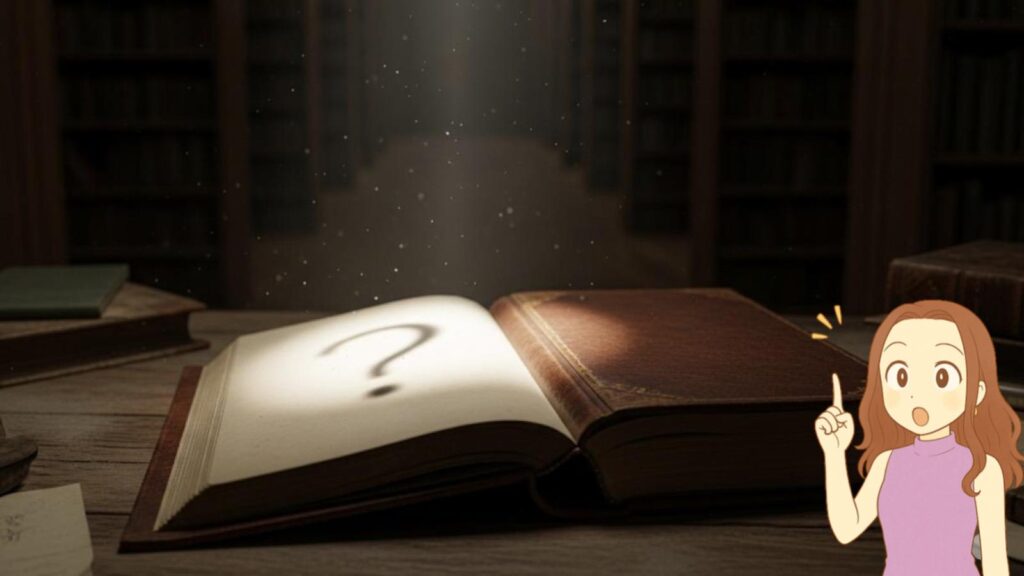
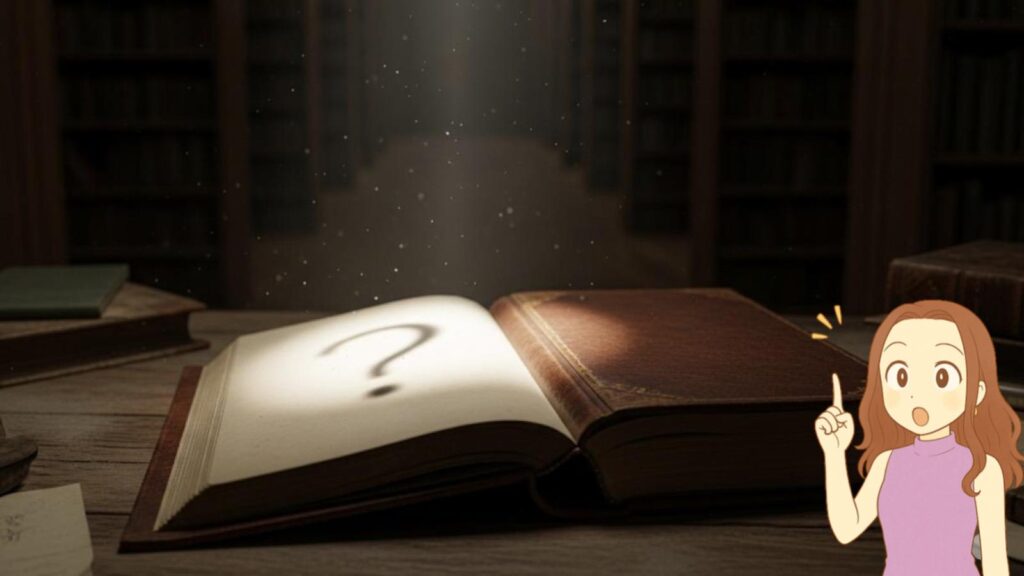
「大英博物館が保有する盗品の一覧を見てみたい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、残念ながら博物館が公式に「盗品一覧」というリストを作成し、公開しているわけではありません。
その理由は、博物館側の立場にあります。大英博物館は、ほとんどの収蔵品について、当時の状況においては「合法的に入手した」という見解を基本としています。そのため、「盗品」や「略奪品」という言葉自体を公式には用いません。
一方で、ギリシャやエジプト、ナイジェリアといった国々は、それぞれが返還を要求している文化財のリストを持っています。これらが、事実上の「返還要求リスト」として存在している形です。例えば、ギリシャにとってはエルギン・マーブルが、ナイジェリアにとってはベニン・ブロンズが、そのリストの筆頭に挙げられます。
このように、何が「盗品」にあたるのかという定義自体が、大英博物館側と返還要求国側とで大きく異なっているのが現状なのです。
略奪品とされるものの割合
大英博物館の収蔵品約800万点のうち、いわゆる「略奪品」と見なされる可能性のあるものは、一体どのくらいの割合を占めるのでしょうか。
この問いに正確な数字で答えることは、実は非常に難しいです。主な理由として、以下の2点が挙げられます。
1. 収蔵品の大部分が未公開・未整理
まず、約800万点とされる収蔵品のうち、常設展示されているのはわずか1%程度の約8万点にすぎません。残りの99%は収蔵庫に保管されています。さらに、全収蔵品の完全なデジタル目録化も完了しておらず、全体像を正確に把握すること自体が困難な状況にあります。
2. 「略奪」の定義が曖昧
前述の通り、何をもって「略奪」とするかの定義が立場によって異なります。博物館側が合法的な購入や寄贈、あるいは発掘調査による入手と主張するものでも、由来国側は「植民地支配下の不当な取引だ」と主張するケースが少なくありません。全ての収蔵品の入手経緯を一つひとつ検証し、現代の価値観で白黒をつけるのは、現実的にはほぼ不可能な作業と言えるでしょう。
これらの理由から、「全体の〇%が略奪品だ」と断定することは誰にもできません。ただ、議論の対象となっているのは、主に古代文明のハイライト的な遺物であり、コレクション全体から見ればごく一部である、というのが実情に近い考え方かもしれません。
大英博物館の盗品をめぐる現在の議論


- 各国との返還要求問題
- なぜ返さない?博物館側の主張
- 2023年に発覚した盗難事件
- 大英博物館の盗品問題を多角的に知る
各国との返還要求問題
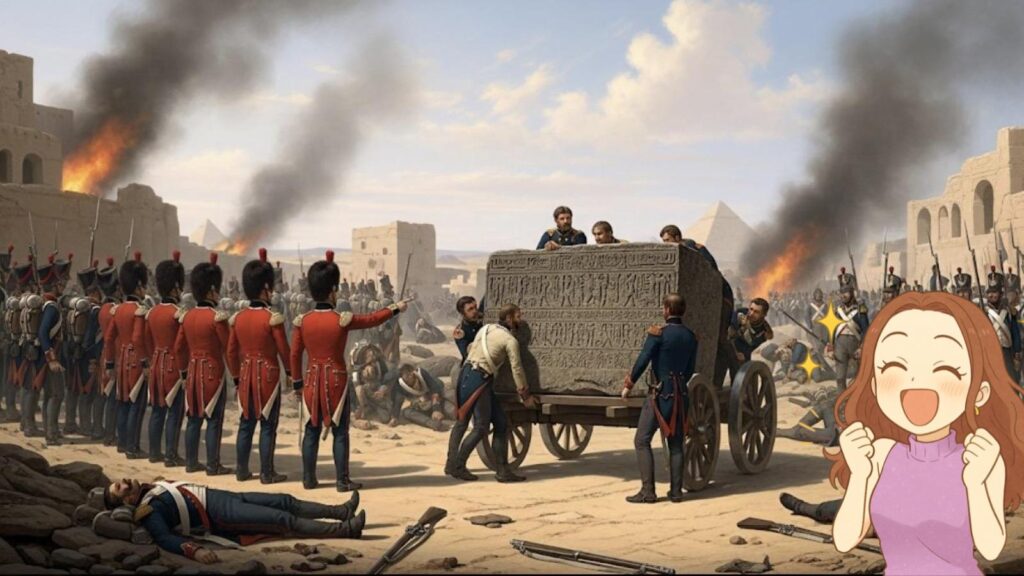
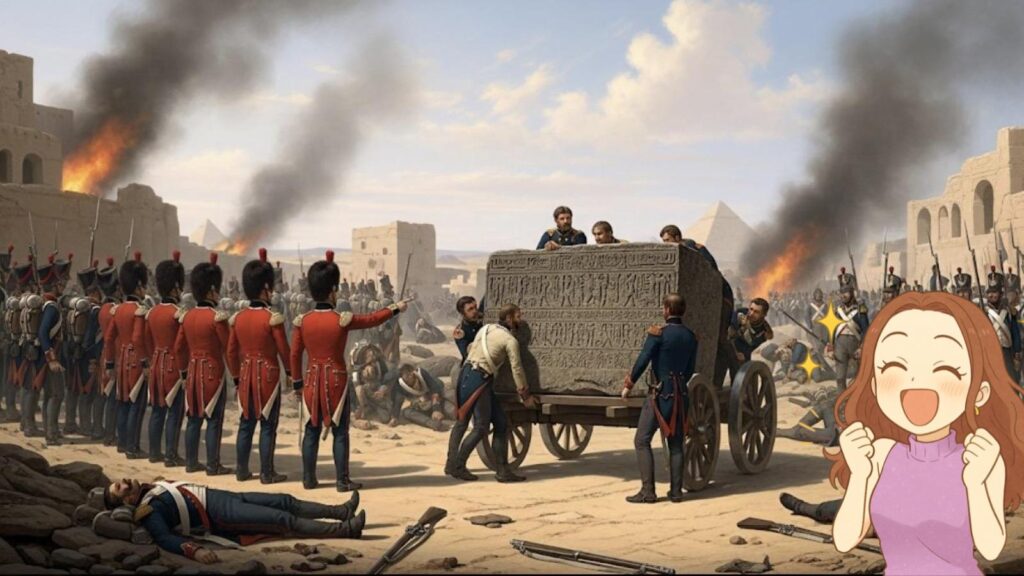
大英博物館に対しては、世界中の多くの国から文化財の返還を求める声が上がっています。これは単に「失われたものを取り戻したい」という感情的な要求だけではなく、国の文化的主権やアイデンティティに関わる、根深い問題なのです。
最も有名なのは、ギリシャによる「エルギン・マーブル」の返還要求でしょう。ギリシャは、パルテノン神殿が自国の文化の根幹をなす象徴であるとして、彫刻群を本来あるべき場所に戻すよう、独立以来ずっと訴え続けています。近年では、返還後の展示場所として最新鋭のアクロポリス博物館を建設するなど、受け入れ態勢が万全であることもアピールしています。
また、エジプトも「ロゼッタ・ストーン」の返還を長年要求しています。古代文明の謎を解き明かした鍵であり、エジプト人にとっての誇りの象徴だからです。他にも、ナイジェリアが「ベニン・ブロンズ」の返還を求めるなど、特に旧植民地だった国々からの要求は切実です。これらの国々にとって、文化財の返還は、植民地時代に受けた傷を癒やし、失われた誇りを取り戻すための重要な一歩だと考えられているのです。
なぜ返さない?博物館側の主張
これほど多くの国から返還を求められているにもかかわらず、なぜ大英博物館は文化財を返さないのでしょうか。博物館側にも、いくつかの主張があります。これを理解することが、問題を多角的に見る上で大切になります。
「普遍的美術館」としての役割
大英博物館は、特定の国のためではなく、世界中のすべての人々のために文化遺産を管理・公開する「普遍的美術館(ユニバーサル・ミュージアム)」であると主張しています。ロンドンという国際的な大都市に文化財があることで、より多くの国籍の人が一度に多様な文化に触れることができる、という考え方です。
保存状態への貢献と懸念
文化財がもともとあった国では、政情不安や環境汚染、管理体制の不備などによって、文化財が危険にさらされる可能性がある、という懸念も示されることがあります。実際、大英博物館が所蔵することで、劣化や散逸から守られてきた文化財も少なくない、という側面も否定はできません。
合法的な入手の主張
前述の通り、博物館は、多くの文化財を当時の法律や慣習に則って、寄贈、購入、あるいは発掘許可を得るなど合法的な手段で入手した、と主張しています。そのため、そもそも「返還」という言葉が当てはまらない、という立場です。
これらの主張は、返還を求める国々の側からは「帝国主義時代の論理の正当化だ」と厳しく批判されることも多く、両者の溝はなかなか埋まらないのが現状です。
2023年に発覚した盗難事件
皮肉なことに、「文化財を安全に保管する」と主張してきた大英博物館自身が、深刻な盗難事件に見舞われました。2023年8月、長年にわたって収蔵品が盗まれ、紛失・破損していたことが公になったのです。
この事件では、紀元前15世紀から紀元後19世紀にかけての宝飾品など、約2000点が失われたとみられています。犯行に関与したとして、30年近く勤務していたベテランの学芸員が解雇されました。
この学芸員は、未登録の収蔵品を狙って盗みを繰り返し、一部をオンラインで安価に販売していたとされています。
この事件は、大英博物館の管理体制のずさんさを浮き彫りにしました。特に、コレクションの多くがきちんと目録化されていなかったという事実は、世界中に衝撃を与えました。
「他国の文化財を安全に保管する」という、これまで博物館が返還を拒む根拠としてきた主張の一つが、根底から揺らぐ事態となったのです。この事件を受けて、当時の館長と副館長が引責辞任し、博物館は組織全体の改革を迫られています。
大英博物館の盗品問題を多角的に知る
ここまで大英博物館の「盗品」とされる文化財について、様々な角度から見てきました。この複雑な問題を理解するための重要なポイントを、最後にまとめておきましょう。
- 「盗品」問題の背景には18世紀からの帝国主義と植民地支配の歴史がある
- 当時の価値観では文化財収集は国の威信を示す行為とされていた
- 特に有名なのはギリシャのエルギン・マーブルやエジプトのロゼッタ・ストーン
- エルギン・マーブルはパルテノン神殿から直接削り取られたもの
- ロゼッタ・ストーンはフランス軍との戦争の戦利品としてイギリスの手に渡った
- ツタンカーメンの黄金のマスクは大英博物館に収蔵されたことはない
- 黄金のマスクは現在カイロのエジプト考古学博物館に所蔵されている
- 博物館が公式に「盗品一覧」を公開しているわけではない
- 何が「盗品」かの定義が博物館側と要求国側で異なっている
- 収蔵品の大部分が未整理のため「略奪品」の正確な割合は不明
- ギリシャやエジプト、ナイジェリアなどが強く返還を要求している
- 文化財返還は国の誇りやアイデンティティに関わる問題とされている
- 博物館側は「普遍的美術館」としての役割や保存状態への貢献を主張
- 2023年には内部の学芸員による約2000点の大量盗難事件が発覚
- この事件により博物館のずさんな管理体制が露呈し、信頼が大きく揺らいだ



イギリス旅行に行く人は下の記事も要チェックです!
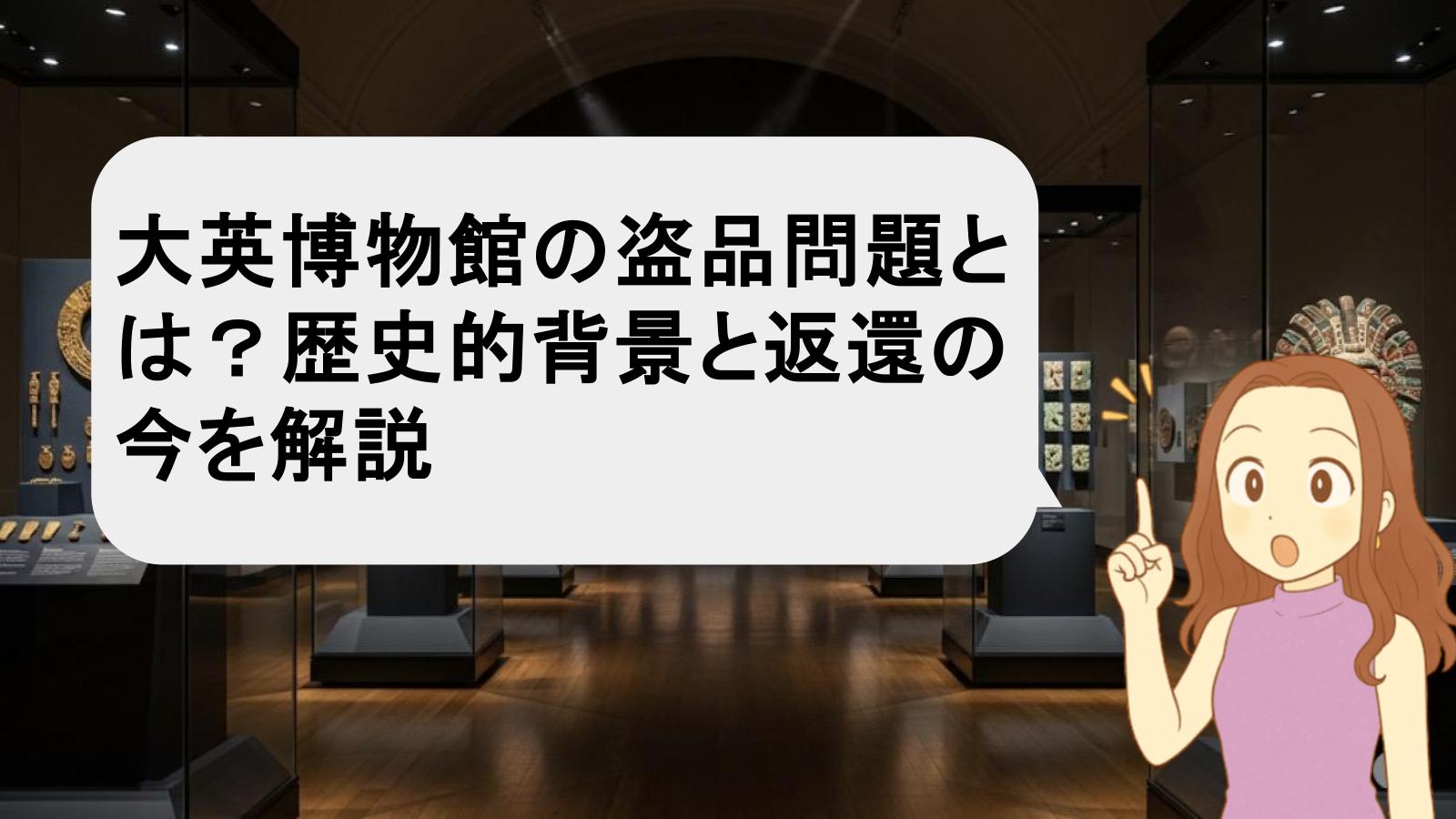
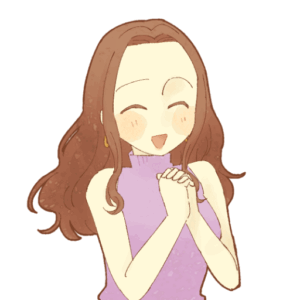
コメント